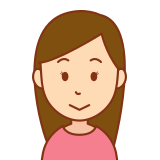
食器が大好きな れら です。
先日、松山市にある工芸ROSAさんが企画する「小鹿田焼展」のお話会に参加してきました。
夕方からの開催でしたが、当日の朝4時に小鹿田(大分県)を出発して松山まで来てくださった陶工さんお2人の、貴重なお話を聞くことができました。
小鹿田焼とは、その特徴
大分県日田市の山間部「皿山地区」で300年以上にわたり受け継がれてきた、伝統的な民陶(みんとう)です。
飛び鉋(とびかんな):金属製のヘラを使ってろくろを回しながら器の表面に幾何学模様を刻む技法です。素朴でリズミカルな模様が魅力。

刷毛目(はけめ):化粧土や釉薬を使って、刷毛やスポイトで模様を施す技法。自然な流れと温かみを感じることができます。

一子相伝:技術は弟子をとらず、家庭内で代々受け継がれるスタイル。窯元は現在も9件ほど存在し、それぞれが伝統を守っています。男性がろくろを回し、女性はその他の工程を担っています。
男の子が生まれない家では親戚から養子をとったりお婿さんを迎えたりと、工夫して継承しています。一子相伝はメディアが大きくフューチャーしすぎなだけである、というお話がありました。
重要無形文化財:2008年に「小鹿田焼の里」として重要文化的景観として選定されました。また、川の水力を利用して土を砕く唐臼の「ギィ、ドン」という音は、心に響く風景音として日本の音風景100選にも選ばれています。
お話会の様子
当日は松山市の花火大会と日程が重なっていましたが、会場には50名以上が集まっており、後半の質疑応答も止まらずで、皆さんの小鹿田焼への関心の高さが伺えました。
実際に飛び鉋や刷毛目の模様をつける際の道具を持ってきてくださり、手に取ってみることができました。昔のゼンマイ時計のばねや長靴のゴムを加工したものを使っているそうで、どこまでも暮らしに沿った器なのだと感じることができました。
他にも、土は足りるのか、小鹿田にも押し寄せる価格高騰やインバウンドの波、陶工のつくりたいものと需要のミスマッチのジレンマなど、多岐にわたる内容をお話をしていただきました。
我が家の小鹿田焼
お話会終了後、この会を企画された工芸ROSAさんで小鹿田焼展があるということで、興奮冷めやらぬまま、行ってきました。そこで今回購入したのがこちらの湯吞み↓

他にも、我が家ではいくつか小鹿田焼を使っています。
飛び鉋の説明でも載せたこちら↓

何の料理を載せても、映えます(笑)
これは我が家の塩壺↓

左が味付けに使う塩で、右はあら塩(パスタをゆでたり、漬物に使ったり)を入れています。
小鹿田焼の壺は、塩の保管に適しています。
小鹿田の土は鉄分を多く含み、焼成後に適度な吸湿性を持ちます。塩は湿気を吸いやすいですが、完全密閉よりもほどよく呼吸する器の方が、固まりにくく使いやすいからです。
また、この美しい壺が目に入ることで、心が豊かになります。
まとめ
今日は、小鹿田焼の魅力をお伝えしました。
小鹿田焼を扱っているお店は全国にあるので、機会がありましたら是非手に取ってみてください。(もちろん、ネット販売をしているお店もあります。)
そしていつか小鹿田焼の里を訪れ、日本の原風景を感じてみてください。

お話会後の写真撮影タイム(笑)
左から、陶工の坂本さん、黒木さん。右端は、鎌倉もやい工芸の久野さん。


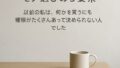

コメント