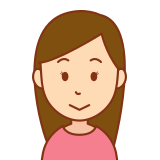
金継ぎ展への参加を検討している れらです。
今日は、以前から検討している金継ぎ展へ出展の申し込みをし、そのことについてブログで報告するつもりでした。
しかし、いざ申し込もうとするとよくないことをグルグルと考えてしまって申し込みをすることができず、今日のブログを書く時間が来てしまいました。(1日1ブログ更新を目指しています)
今日は、その裏の隠された思いを深掘りしてみようと思います。
気持ちを深掘り
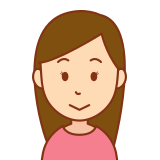
出展したい気持ちを阻むものは、何だろう?
①出展申し込みの画面で、本名を入力する所がありました。
私は本名が珍しくて覚えられやすいので、人物が特定されたりそこに注目が集まるのは嫌だなあと思いました。
②出展申し込みの画面で、屋号とSNSを入力する所がありました。
私が金継ぎの活動で使っている屋号は、金継ぎにちなんだ名前でとても気に入っています。
しかし私の金継ぎの技術はまだまだ未熟で、そんな私がこの屋号を名乗るのは恥ずかしい、という思いがあります。
またSNSも同様で、映える写真を載せられていないのがコンプレックスとなっています。
解決策
①本名について
→器を送ることになるので、本名は必要。(配送業者さんが困ってしまいます)
展示の時に、本名は記載しない旨を主催者さんへお願いする。
②屋号、SNSについて
屋号を持たず、趣味で金継ぎをされている方も出展されるそうです。
その方は、本名での出展になる?→私は本名も出したくない→偽名もしくはペンネームでの展示をお願いする。
SNSも出したくなかったら、出さない。
ここまで書いて、だいぶ気持ちの整理がついてきました。
配送時は本名を伝えた方がいいけど、展示は本名でもなくいいし、今使ってる屋号を出さなくてもいい。SNSも記載しなくてOKですね。
だいぶ出展のハードルが下がってきました。
ここで、ChatGDPにも聞いてみることに↓
① 本名の入力が求められることへの抵抗感
- 事務局に問い合わせる
「本名の公開範囲」について事務局に確認してみましょう。
例:「申し込み画面で本名の入力が求められましたが、展示会のパンフレットや会場で本名が公開される予定はありますか?屋号のみでの表示は可能でしょうか?」- 屋号での出展名を希望する
多くの展示会では、出展者名として屋号を使うことが可能です。本名は事務処理用で、外部には出ないケースもあります。- プロフィール文で視点をずらす
もし本名が公開される場合でも、プロフィール文や展示紹介で「作品や哲学」に焦点を当てることで、名前への注目を和らげることができます。
例:「金継ぎを通して“継ぐこと”の美しさを探求しています。日々の小さな修復が、心の景色を変えてくれると信じています。」② 屋号やSNSに対する「未熟さ」や「映えない」ことへのコンプレックス
- SNSは“記録”としての美しさを意識する
映える写真でなくても、「日々の修復」「道具の手入れ」「欠けた器との対話」など、あなたらしい視点での投稿は、見る人の心に響きます。
例:「映えないけれど、心に残る」写真シリーズとして、金継ぎの途中経過や道具の並びを投稿するのも素敵です。- 「未熟さ」を言葉にしてしまう
展示会のプロフィールやSNSの自己紹介に、「まだまだ学びの途中ですが…」と書くことで、見る人との距離が縮まり、応援される存在になります。
例:「金継ぎの道を歩き始めたばかりですが、欠けやヒビに寄り添う時間を大切にしています。」- 屋号は「今の自分の理想」や「向かいたい方向」を表す旗のようなもの。技術が未熟でも、屋号があることで「育てていく場」が生まれます。
例:「屋号に込めた想い」を展示紹介文に添えることで、未熟さがむしろ誠実さとして伝わります。
なるほど!
プロフィール文で視点をずらす方法や、展示紹介文を上手く使う方法もあるんですね!
展示紹介文を考えるのは大変そうだなと思っていたのですが、上手に使っていきたいなと思いました。
余談
このブログを書くにあたり、手持ちに使えるアイキャッチ画像がなかった為、これもChatGCPに作成を依頼しました。
非常に美しいのですが、実際にこれを金継ぎで仕上げるとなると、そうとう大変です。。。(苦笑)




